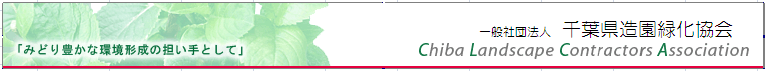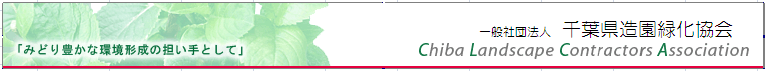■ 安全管理の推進
安全は危険状態をいかに小さくするか、安全を保ち続けるための意識と努力が大切です。安全はただ事故のない状態のことではない。いかに安全計画をたて実行していくか絶えず意識改善をしなければ安全推進はおぼつかない。
ではどのようにしたらよいのか意識改善の取り入れとして、ハイリッヒの法則というものがある。1件の重大事故(災害)発生の背後には、軽傷事故が29件、ヒヤリ・ハットが300件あるという法則です。
「いつものことだから、この程度はたいした事故につがらない」という気持ちがややもするとミスを見逃したり、見て見ぬふりをすることが当たり前となり、やがて重大事故につながることがあります。
では、その改善対策を具体的にどうするか。
- 事故を予見し、発生した事故も記録する
(1) 安全パトロールで事故を予見する
(2) 安全について現場で意見を聞く
(3) 些細な事故でもすべて記録し、データとして共有する
- 予見事故・発生事故を反省しその予防策を立てる
(1) データを元に緻密な予防策を立てる
(2) 現場の意見・知恵と工夫を出し合い予防策をまとめる
(3) 現場意見とデータをあわせ予防策を策定する
- 予防策を実施に移す
(1) 結果を見る
(2) 実践は継続する
- その結果を検証する
(1) 予防策の効果を根気よく検証する
最後に
すばらしい予防策(予知)でも参加する人が本気にならないと絵に描いた餅となります。安全・災害防止改善活動は全員参加、現場と一体となり互いに協力し災害は自分たちで守るための意識を創りだす事が大切です。
安全管理推進のポイント
- 安全週間等の期間中だけでなく永続的な意識をもたせる
- 安全の必要性の教育・訓練・参加
- 法令順守・法令改正に伴う対応策設定・啓蒙活動
- 働く者とその家族,顧客に安心してもらえる風土
- 一人ひとりがゼロ災害を365日意識できるような組織体制
- 社会的責任・安全第一を重んじこれを活動の中心的な位置付とし、災害防止の管理業務の仕組みを作る。